ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。 18代インド首相 前グジャラート州首相

BFI ヘッドのアジェイ・シン (左)、IBA チーフのウマル・クレムレフ (C)、世界チャンピオンのニハット・ザリーン。AFP
ニューデリー : インドは 2023 年にニューデリーで女子ボクシング世界選手権を開催する予定であり、人工知能に基づく新しい審査システムが初めて使用されると、ゲームの世界統治機関 (IBA) が水曜日に発表した。
インドは、世界統治機関に必要な料金を支払わなかったために男子イベントの開催権を剥奪されてから 2 年後、女子プレミア イベントを開催します。
インドはこれまで男子世界選手権を開催したことはありませんが、2006 年と 2018 年にニューデリーで開催された同国でエリート女子大会が開催されるのは 3 回目です。
インドはまた、2017 年に女子ユース世界選手権を開催しました。
国際ボクシング協会(IBA)とインドボクシング連盟(BFI)の間で、水曜日にIBAのウマル・クレムレフ会長とBFIのアジェイ・シン会長の出席の下、了解覚書(MoU)が調印された。「女子世界選手権は 2023 年 3 月にデリーで開催されます」とシンは言いました。
「女子ボクシングは大幅な改善を見せており、私たちは世界のトップの国の 1 つです。前回の版では 3 位でしたが、それを改善することを目指しています。約 75 ~ 100 か国、約 1,500 人のボクサーとコーチからの参加を期待しています。チャンピオンシップでは、歴史的な試合レビュー システムも導入されます。」
インドが2023年世界選手権を開催:BFI

サビタ・プニア。ホッケーインド
サビータがFIHネーションズカップでインドをリード
ニューデリー : インドは水曜日に、スペインのバレンシアで 12 月 11 日から 17 日まで開催される女子 FIH ネーションズ カップ ホッケー トーナメントの 20 人のメンバーのチームを指名し、ミッドフィールダーの Navjot Kaur は、今年初めの Commonwealth Games を欠場した後に戻ってきました。
ゴールキーパーのサビータ・プニアが引き続きチームを率い、ベテランのディフェンダー、ディープ・グレース・エッカが彼女の代理を務めます。
FIH Women's Nations Cup は、このトーナメントのチャンピオンが FIH Women's Pro League 2023-2024 シーズンに昇格するため、国際カレンダーの重要な試合です。
インドはチリ、日本、南アフリカとともにプール B にグループ化され、プール A はアイルランド、イタリア、韓国、スペインで構成されます。
インドはトーナメント初日にチリとのキャンペーンを開始します。若手フォワードのビューティー・ドゥンドゥンが代表デビューを果たす準備は万端で、経験豊富なナフジョット・カウルは新型コロナウイルス感染症の影響でバーミンガム・コモンウェルス・ゲームズを欠場した後、チームに復帰する。
チームにはリザーブのゴールキーパー、ビチュ・デヴィ・カリバムも含まれており、ドラッグフリッカーのグルジット・カウル、ニッキ・プラダン、ウディタ、イシカ・チャウダリーがエッカと共に守備ラインを形成します。ミッドフィールドには、ニシャ、サリマ テテ、スシラ チャヌ ハリバム、モニカ、ネハ、ソニカ、ジョティ、ナヴジョット カウルが、フォワード ラインには、ヴァンダナ カタリヤ、ラルレムシアミ、ナヴニート カウル、サンギタ クマリ、ドゥンドゥンが配置されます。
8 月の CWG で最近銅メダルを獲得したインドは、2021-22 FIH プロ リーグでの初出場で印象的な 3 位を獲得しました。2017(平成29)年2月19日(日)14:00~
今治市宮窪町宮窪1285
村上水軍博物館 1階講座室
ヤギといっしょに ○○づくり
~ミルクや肉を味わうだけじゃない!イマドキのヤギ活用~
ヤギと始まる新たな物語
- Goat and the new story which starts -
~ふるさと再生ヤギプロジェクトの取り組み~
広島ミニヤギ牧場 代表
1級愛玩動物飼養管理士 菅原 常司
1 はじめに
ヤギを活用した「ふるさと再生ヤギプロジェクト」に取り組んでもうすぐ3年になります。
本提案は,このプロジェクトの目的と具体的な事例をいくつか紹介しながら,情報交換をさ
せていただき,ヤギの役割を見直し,ヤギの持つ多様性や新たな可能性をいっしょに
考え,次の若い世代の人たちに伝える機会となることを願っています。
2 今,畜産・農業は…(ヤギ飼養の推移からみえてくること)
1961年,農業基本法によって農業の大規模化が打ち出され,日本の畜産・農業
の生産構造は大きく変わってきました。畜産業においては,より経済効率の高い家畜
を飼うことが奨励され,「経済家畜/産業家畜」として『牛,豚,ニワトリ』の飼育が
主流となってきました。同時に農業では”米は米農家,野菜は野菜農家”というよう
に「農業の専門化」が進んでいきました。ヤギの飼育頭数は1998年以降,農林水産
省によるヤギ飼養頭数の調査が行われなかったため,最近の飼養頭数に関する情報は
乏しく,正確な数は把握できていません。推定では,全国に約2万頭(平成26年(2
014)だと言われています。そして,乳牛は約150万頭,豚は約1000万頭が飼
育されており,家畜の中でも特にヤギの飼育頭数はケタ違いに少なくなっています。
しかしながら,世界を見渡すとヤギは着々と増え続け,国連食糧農業機関(FAO)
の統計によると世界で飼育されている頭数は,2000年に約7億5000頭だったのが,
現在は約10億頭と言われています。
このような中,日本の農産食品の自給率は下がり続け,昭和40年度に73%だっ
たのがその後,約50年の間に食糧自給率は39%(平成27年度)まで下がり,食料
の大半を外国からの輸入に依存するようになってきました。このままだと日本の食料
自給率は大丈夫なのか心配になってきます。それは,食料の確保は世界の天候や食糧
問題に左右されやすく今後,国内の農業生産だけでは食べ物が足りなくなってしまう
おそれがあるからです。テレビ放送では,「グルメ番組」が多いのですが,土地資源を
利用しないまま,世界的にも恵まれた温暖な気候の中で食料を海外からの購入に任せ
ている日本という国は,食べ物の本質を理解していないように思えます。
※ 食糧自給率…国内の食料消費を国内の農業生産でどのていどまかなえるかを示す指標
日本では,一時期のヤギブームも終わり,日常生活の中でヤギを目にすることが少
なくなってきました。愛媛県においてもヤギは減少し,今や「希少家畜」となりつつ
あります。
愛媛県 山羊飼養の推移 資料(農林水産省「畜産統計」より)
年 1957 (S.32) 1975(S.50) 1987(S.62) 1988(S.63) 2007(H19) 2008(H20) 2014(H.26)
戸数 1 万 1610 490 70 80 10 2 53 戸
頭数 1 万 1610 590 100 130 18 4 154 頭
全国 66 万 9200 11 万 0800 4 万 7600 4 万 1000 3 万 6500 1 万 4702 2 万 164 頭
(1) 日本のヤギ飼養の転換期
これまで国内のヤギ種畜改良を率いてきた「家畜改良センター長野牧場」が,ヤギ
・ウサギ業務を縮小することになりました。家畜改良センターの事業は,政府の独立
行政法人の見直しを受け,その規模の縮小や業務の民間委譲が求められました。総務
省政独委勧告の中に『家畜の改良・増殖業務の重点化(乳用牛・肉用牛・豚・鶏の4種
畜)』が盛り込まれ,ヤギやめん羊,ウサギにおける種畜配布が廃止されました。
ヤギに関しては,畜種配布業務の民間委譲と普及啓蒙への特化に移行し,2009
年(平成21年)度末をもってヤギ(日本ザーネン種)の種畜配布業務を民間を中心とした
体制へ移し,廃止することが決定しています。シバヤギは2007年(平成19年)度
までに大学等研究機関へ,ウサギは2007年(平成19年)度末をもって種畜配布業
務を終了しています。つまり,これからの日本のヤギは,民間が背負うことになりま
す。また,BSE問題の発生以来,ヤギを処理していた屠畜場(食肉センター)が年
々少なくなっているため,ヤギの搾乳農家は雄ヤギの処理に困っているのが現状です。
(2) 日本の農業の転換期
畜産・農業の仕事は,家畜,農地や作物の知識と経験を持った人が,土との対話や
自然と共生・交流をしながら,ヒトの生命をつなぐ,栄養源をつくる大切な営みです。
今,日本の農業は大きな転換期を迎えています。平成21(2009)年12月,農
業を成長産業とし,農村地域での仕事とビジネスの機会を増やし,農村地域を魅力的
な生活と居住の場にするとして,「平成の農業改革」が始まりました。
.
この改革には,「農地利用権の緩和(農地の所有から利用へ)」があります。農業経
営の大規模化と効率化を目的に,農地の所有と利用を分け,農地及び採草牧草地の権
利移動や転用(農地不動産ビジネス)の規制を緩和し,農地の有効な利用を促進する
のがねらいです。さらに,「企業型農業経営の促進」です。企業が農業生産法人へ出資
して農業分野に参入し,農業生産法人の経営参加や農業生産法人を設立したりするこ
とができるようになりました。
しかしながら,現行の生産調整制度の廃止(平成30年)や企業が農業に参加するこ
とで,農業の担い手不足がさらに加速し,中山間地域の農地の荒廃(耕作者不在の放
棄地や遊休地の増加)や集落営農システムの弱体化,農地の売買・転用が進むなど,
農業環境の悪化を引き起こすのではないかと危惧しています。
それは,政府の農業生産基盤の維持,経営の安定化に向けた対策にもかかわらず,
農業就業人口は,2016年2月1日現在192万2200人で1990年と比べると
4割程度まで急減し,離農が進んでいます。また,団塊の世代の方が定年を迎え,第
一次産業へと回帰する方もいらっしゃいます。団塊の世代で定年退職を機に就農が増
えたとみられる65歳~69歳は36万8300人と増えましたが,農家全体の半数近くを
占めている70歳以上の高齢農家の方が88万5500人で,高齢のために離農する人が
増えています。そして,40歳未満の若手の就農者は減り続けています。特に,29歳
以下では,4万8200人,30~34歳は3万1200人,35~39歳3万8300人と,農
業の担い手不足に歯止めがかかないのが現状です。
けれども,高齢化=人口減少=農業就業数の減少という数字だけを注目するのでは
何も解決しません。例えば,定年退職を契機とした農村への定住志向がみられます。
農村では定年がなく,65歳になったからといってすぐに生産現場や地域活動から退
くわけではありません。むしろ,退職して時間的な余裕ができた人が新たな地域の担
い手として期待されます。また,都市に住む若者を中心に,農村への関心を高め,新
たな生活スタイルを求めて都市と農村を行き交う「田園回帰」の動きもあります。
今は,「価値観の転換」が大切だと思います。その土地(風土)にあった農業や漁業,
地元にある資源を使った観光など,工夫をすれば収益をあげられるものがあります。
しかし,地域の人は,生まれ育ったふるさとを知っているようでよく知らないこと
があります。「そこら辺にあるものが売れるはずがない」とあきらめ,地域にある価値
を見逃してしまう可能性もあります。都市からきた人は,地域の新たな価値に気付き,
アイディアを出すことができます。そうした違う目や価値観を持った人が地域に入っ
てくることは,町に新しい産業が生まれる可能性がどんどん広がっていきます。
(3) エコな生き方から「ロハス」な生き方へ
これまでは,エコライフ(環境にいい生き方)という生活意識が主流でした。しか
し今は,シンプルライフやスローライフを志向する「ロハス」な生き方を求める人が
増えています。それは,社会(都市)のストレスから距離を置き,自然環境の中で,
自然の幸に恵まれながら,ゆったりとした生き方を持ちたいと考える人たちです。
今,このロハス(LOHAS)な生き方(健康と環境問題への関心を持つ生き方)へ
と少しずつ意識が変わってきています。
つまり,健康生活を送るために自然環境を意識・配慮した生活を送ろうと「オーガ
ニック食品や自然食品,無農薬野菜,無添加食品」を選んだり,体の健康を守る上で
環境に優しい商品を選んだり,健康志向や環境に優しい生活用品,サービス,シンプ
ルライフやスローライフな暮らしを求める人たちが増えています。こうした環境に配
慮しながらも,自分のライフスタイルを好む年配の方や若者たち(ロハスピープル)
の支持を受けて,ヤギの注目度は高まってきています。
これからは,「ロハスな生き方を考えた畜産・農業の可能性」を模索していかなけれ
ばならない時代となっていると考えます。
ロハス(LOHAS)…Lifestyles Of Health And Sustainability(健康や自然環境保護・環境問題のことを
考えた生き方=ライフスタイル
3 ヒトの生き方とつながるヤギへ
遠く県内外より,下蒲刈島の小さな集落,大地蔵地区にある「広島ミニヤギ牧場」
までヤギを求めて来られます。年代も様々です。その理由として,
①ヤギを見たことがないので見たり,さわったり,レンタルしたい
②ヤギ乳を飲みたい。牛乳は,「乳糖不耐症」といって飲むとお腹を壊しやすい
(ヤギ乳は,含まれる脂肪球が牛乳に比べて小さいので消化されやすく,牛乳
アレルギーの人も飲用できる特長がある)
③田舎暮らしで有機農業を始めた,または,これから始める準備をしているので
土地を維持するのにヤギを飼いたい
④定年を機に土地を購入,地方へ移住して農業をするのでヤギを探している
⑤除草で困っている,草刈り機や除草剤の代わりにヤギを飼いたい
⑥鳥獣害対策としてヤギを飼いたい
⑦ヤギは人によく慣れるので,家族として,ペット(愛玩動物)として飼いたい
⑧ヤギは珍しいので,イベントで集客を目的にレンタルしたい
⑨子どもの心の教育のため,ヤギを飼う体験をさせたい
⑩ヤギは癒し効果があるので,学校や老人ホームで交流やふれあいに利用したい
⑪発達しょう害の子どもや心にしょう害のある方へヤギの飼育経験やふれあいを
通して利用したい(アニマルセラピー)
⑩ヤギを活用して地域・ヒトを元気にしたい(地域おこし)
このように,新たな利用価値を求めて来られる方がおられます。県内外から家畜を
農業の一部に取り入れた有畜複合農業(ヤギの糞を堆肥にして畑に混ぜて土(作物)
に取り組みたい方や小・中・高等学校,公共施設,介護施設,老人ホームからヤギレ
ンタルの依頼,退職後はヤギを飼って暮らしてみたいなどの相談や要望があります。
これらのことは何を示唆しているのでしょうか?
それは,これまでヤギはミルク,乳製品や肉,皮,
毛など,ヒトの生活に役立てる役割から「ヒトの生
き方とつながるヤギ飼養」へと変わり,食の安全性,
健康と環境問題を意識した利用やヒトの心を癒すこ
とを目的に飼う時代になってきているからだと思い
ます。
4 下蒲刈町の概要
呉市下蒲刈町は,周囲が15.8km,
人口は約1500人の小さな島です。平
成12年1月18日に本州と下蒲刈島に
安芸灘大橋がかかり,島民の念願であ
った「安芸灘とびしま海道」は,呉市
の6つの島と愛媛県今治市岡村島の1つ
の島を加え,7つの橋でつながってい
ます。
海道の入り口にかかる安芸灘大橋は,呉市川尻町と下蒲刈島を結ぶ,長さ1175m,
幅員16mのライトブルーのつり橋で,都道府県で整備された「一般県道のつり橋」と
しては,日本最長の橋です。
5 下蒲刈町の課題
① みかん価格・消費量の低迷により収入が不安定
② 農家の担い手(働き手)の減少
③ 高齢農家の増加と離農による後継者不足
④ 柑橘栽培の技術継承が難しい
⑤ 空家(島を離れる人)の増加
⑥ 人口(若者)の減少による町の活力低下 →ヤギ利用
⑦ みかん/レモン苗木の改植事業の遅れ →ヤギ利用
⑧ 維持・管理が十分されていない農道 →ヤギ利用
⑨ 山林や竹林,園地の荒廃,耕作放棄地,休耕地の増加 →ヤギ利用
⑩ 鳥獣被害(イノシシ・カラス・タヌキ)の増加 →ヤギ利用
町民の悲願であった橋も架かり,本土と結ばれ陸続きになって
くらしは便利になり,島の主要産業であるみかんづくりの普及が
進むはずでした。しかし,かつて「天まで届く…」と盛んだった
段々畑のみかん山が今,荒れています。
その理由として,まず,みかん消費量の減少や1991年4月か
ら「牛肉とオレンジの輸入自由化」により安い外国産のオレンジが季節を問わず店頭
に並び価格は低迷し,みかん栽培だけでは生計がなり立たなく,後継者も育たなくな
ってきました。
また,みかんの木や生産農家の高齢化が進み,栽培をあきらめて離農する人や空家
がみられるようになりました。そして,橋が架かって,買い物や通勤・通学の便利な
町で暮らす人,進学した後,就職を収入の不安定な農業から安定した職業を求めて,
親元から離れて暮らす人が増えてきました。その結果,様々な被害が追い打ちをかけ
るように起こってきました。
古い木は,カミキリムシ,カイガラムシなど病害虫の被害で枯れ,
農作業の難しい急傾斜のみかん畑や車の入らない園地は除草ができ
ず手入れ不足で放棄されています。
山林は,松食い虫の被害で赤松林が倒れ,畑は草や雑木,竹林に
おおわれてきたために,イノシシ(農作業中,イノシシと遭遇した
時の不安,みかん食害,根を掘る,枝を折る,石垣を破壊する)やタヌキ,カラスの被
害に悩まされるようになりました。
また,農家の担い手難のため,植え付けられたみかんの木は古木となり,新しく苗
木を植える改植事業も思うように進んでいないのが現状で,「栽培技術の研修会を企画
しても人が集まらない,傾斜地のみかん畑は草刈り機が危険で行けない,重いみかん
箱を運んだり,防除したりする作業は体力的にできない」等,暗い話題ばかりです。
このように,町の基幹産業であるみかん・レモン栽培は,農地・農道の保全,農業
従事者の高齢化,それに伴う栽培技術の継承が難しくなっています。このままでは,
町の活気は失われ,山林の荒廃や耕作地の放棄が進み,「みかん・レモンの島」として
受け継がれてきたふるさとは,亡失してしまうのではないかと感じています。
6 広島ミニヤギ牧場&菅原オレンジ農場
広島ミニヤギ牧場は,呉市下蒲刈町の大地蔵地区にあり,海を
見渡せる小高い丘のみかん園の中にある,こぢんまりした牧場で
す。私が教師をしている時は,土日に親元へ帰って農業に従事す
る「ウィークエンドファーマー」で,草刈り機で除草するのが精
一杯でした。そんな姿を見て母からは「畑はもうやめよう」と言
われてきました。
しかし,「少しでも自分にできることからしよう」と決め,退職を機に平成26年4
月から,みかん・レモンの収穫体験や海で遊んだり,ミニヤギとふれあったりでき,
ほっとできる農園にしたいと願って牧場を移転し,新たに牧場とミニログハウスをセ
ルフビルドして始めました。
牧場には現在,トカラヤギ,韓国ヤギ,アルパインを12頭を育てています。
7 ミニヤギを飼い始めた理由
ヤギを飼い始めたきっかけは,私のクラスにいた2名の不登校
児童でした。感受性が豊かな子どもたちが好奇心を持ち,笑顔と
優しさにあふれ,少しでも学校に近づける機会はつくれないもの
かと模索し,小さな子ども達でも扱える小型のミニヤギを飼うこ
とにしました。最初は,3ヶ月になるシバヤギのメス1頭から始
め,子ども達に飼育のお手伝いをしてもらいました。その後,ト
カラヤギのオスを飼って子ヤギも産まれ,ヤギを車に乗せていっ
しょに学校に登校するようにしました。その結果,部屋に閉じこ
もりがちだった児童はヤギの世話をすることを通して,元気に学
校に来られるようになりました。
8 有畜複合農業の取り組み
何もかも手探りの状態からのスタートでした。そして,ヤギを活用した有畜複合農
業を1から勉強して,ヒトも自然も生態系に影響の少ない農業を
めざしました。“You are what you eat.(身体は食べたものからでき
ている)”と言います。「食」という漢字は,”人を良くする”と書
きます。「食べる」という行為は,人の命をつなぐことです。良い
食材は,地域・風土に育まれた自然環境が作り出してくれます。
初めに,放棄していた園地に,休憩できるミニログハウスを建
てました。そして,ヤギと牧場を下蒲刈町に移しました。廃材を
利用した手作りのヤギ舎を建てた後,鉄柵で囲いました。次に,
古いみかんの木を伐採してヤギを自由放牧しました。残った木や
枝は,燃やしてから草木灰とヤギの厩肥を畑に入れてから,苗木
を植えました。その後,みかん園の手入れをヤギといっしょに取り組みながら,ヤギ
の活用とみかん・レモンづくりを組み合わせた農業を計画し,少しずつ始めました。
9 地域に支えられたこと
牧場を始めて困ったことは,ヤギの多頭飼いの問題です。羊と違ってヤギには,明
確な社会的順位が存在します。個体間で頭突きでの争いが激しく,特に飼料の採食競
合がみられます。そのために,新たにヤギ舎を建て,雄と雌を分けて飼料の競合を緩
和し,メスや弱い子ヤギを守るために餌箱も増やしました。
次に,飼育するのに必要な面積は1頭あたり2 ~8 ㎡ が良いとされ,竹林のあっ
た広い場所へヤギ舎を増築しました。しかし,放牧管理上の問題として,みかんの果
実,枝を食べたり,脱柵や雄が柵を破壊するなど,柵に関わるトラブルがあり,その
度に補修してきました。
また,繋牧して除草する際,つないでいるからと安心していたのですが,親子で放
牧すると,子ヤギがロープで首や足に絡まることがあるので,必ず互いの距離をとり,
必ず様子を見に行くようにしました。始めた当初は,餌と騒音(鳴き声)の問題があ
りました。しかしこれは,地域の方や教え子達から支えられました。朝や夕方にヤギ
が鳴くと,地域の人が来て「ヤギが腹をすかせて鳴いているようだ,野菜を持ってきた」
「餌はあるのか?イチゴの葉を捨てていたけれどヤギに食べさせてくれ」「剪定した枝が
あるがヤギは食べるか?」と,鳴き声への理解や餌の世話をしていただいています。
それがきっかけで,「地域に貢献できることはないか?ヤギといっしょに何かできな
いか?」と,考えるようになりました。
10 ふるさと再生ヤギプロジェクト
今起きている地域の問題は,自分たちが直面する切実な問題なわけです。ですから,
まずは自分から問題提起して,立ち上がってスタートしない限り,一歩も前には進ま
ないと考えました。先ずホームページを立ち上げて,町の魅力,文化伝承に情報発信
の場をつくりました。そして,ヤギを活用して何か人に役立つことはできないか考え
て最初に,ヤギのボランティア除草を始めました。それから,「1級愛玩動物飼養管理
士」の資格を取得し,「第一種動物取扱業(販売・貸し出し)」の許可をとって,ミニ
ヤギの譲渡・貸し出しも始めました。
ふるさと再生ヤギプロジェクト
高齢化 みかん園の耕作放棄地 荒廃地
ミニヤギを利用してできることはないだろうか…
「ふるさと自慢づくり/ヤギを活用した有畜複合農業」
プ ラ ン
(1)「ヤギの島に」…ヤギとふるさと情報を発信する
(2)「ヤギの利用」…農地の保全・管理の理解(ヤギの除草ボランティア)
(3)「ヤギとみかん園」…ヤギとみかん&レモンを組み合わせた有畜複合農業
(4)「ヤギの繁殖・譲渡」…ヤギ活用の周知と飼育したい方へ譲渡
(5)「メンタルヘルス」…学校・介護施設・老人ホームへ貸し出し
農地保全への理解と促進&地域コミュニティの活性化
アクション
(ア)みかん園の活用,海の見える丘へ「ミニヤギとふれあえる牧場」づくり
(イ)ヤギの除草ボランティアを行い,園地の保全・管理のお手伝い
(ウ)ミニヤギを繁殖し,譲渡・貸し出し
(エ)ヤギの糞の堆肥化と草木灰を利用したみかん&レモンの低農薬・有機栽培
(オ)みかん&レモン,ヤギ利用の様子をネット(ホームページ)で発信
(カ) 郷土の記憶(魅力)を掘り起こして記録,町のよさをネットで発信
10 「ふるさと再生ヤギプロジェクト」の取り組み
(1)地域の人とつながる 除草ボランティア
最初にしたのがヤギのボランティア
除草でした。除草にヤギを貸し出し
自分達でヤギを車に乗せて畑へ。2
度目のヤギレンタルも希望され,ヤ
ギの除草効果を実感され,耕作地を
広げたいと意欲的です。
(2)保育・幼稚園児とつながる
子ども達がみかん園でヤギと楽しく
過ごせる場所として町広報誌で掲載。
口コミで広がり,園児が遊びに来る。
祖父母や保護者と再度,見学に来ら
れて地域コミュニティの輪が広がっ
ています。
(3)小学生とつながる (総合的な学習・生活科)白岳小,広小,下蒲刈小
生活科や総合的な学習の時間に学校
へ出向き授業したり,社会見学で牧
場見学の依頼。エサやり,だっこの
体験を。動物も接し方,家畜の役割
やヤギの愛らしさを肌で感じとって
いました。
(4)中学生とつながる (呉市立下蒲刈中学校)-ふるさと探訪-総合的学習
町で自慢できることを探しに牧場へ。
調査したことをまとめ,情報発信。
かつて地域にヤギ,羊,牛がいた事
やヤギ牧場の取り組みを知り,「ふる
さと自慢をみつけて誇らしい気持ち
になった」そうです。
(5)高校とつながる (広島県立福山誠之館高等学校)
18名の生徒がヤギの世話係に立候
補し,交代でお世話を。他校の教師
や生徒の話題から福山より牧場見学
の方も。ヤギの世話を通して責任感
や優しさを養い,畜産に興味を持っ
てくれることを願っています。
(6)ヤギの里親でつながる (岡山県備前町/安佐北区白木町/八千代町)
飼うことが困難になったヤギを引き
取りその後,休みには牧場へ会いに
来てくれます。好きだった餌を与え
たり声をかけたり,なでなでしなが
. . . .
ら,ヤギとの思い出がよみがえり,
懐かしい気持ちでいっぱいに。
(7)介護施設・老人ホームの方とつながる (セラピーアニマルのヤギ)
年々ヤギレンタルが増えています。
お年寄り,障がい者,病床の方,デ
イサービス,リハビリ中の方,施設
の職員等,「ヤギがいるとホッと気持
ちが和らぐね」「ヤギを見るのが毎日
楽しみ」とみんな笑顔に。
(8)障がいをもつ子とつながる (神戸市,倉敷発達障がい者支援センター)
自閉症や発達障がいのある子に,学
習面や社会性・コミュニケーション
といった能力を伸ばす支援としてヤ
ギを活用した症状緩和や状態に適し
た支援,ふれあえる環境を整えるこ
とは可能か視察に来られました。
(9)商店街のイベントでつながる (呉本通り商店街)
「商店街を活性化しよう」とヤギのふ
れあいコーナーを設け,集客数を増
やしたいと協力依頼が。多くの家族
連れや若者が集まり,記念写真やツ
イッターなど口コミで広がり,ヤギ
のふれあい広場が盛りあがりました。
(10)愛媛県のイベントでつながる (八幡浜,今治,新居浜,三島・川之江,西条,松山)
岡村島からフェリーで今治へ。広告
会社からの依頼で自動車販売店のイ
ベントに四国へ6回行ってきました。
ヤギの譲渡や子どもへヤギレンタル
はできないか等の相談もお受けしま
した。
(11)呉市長さんとつながる
島巡りで市長が町へくることになり
ました。みかんがないこの時期にど
うしよう…ということで「島のお宝
ミニヤギ登場」市長さんとヤギのふ
れあいが実現しました。下蒲刈町=
ヤギの島でアピール
(12)ロハスな人たちとつながる NPO法人 アロマテラピーグループ(広島市)
みかんの花咲く時期は山全体が良い
香りに包まれ,香りと花に癒される。
「みかんのお花見+ヤギ見学」,「み
かん狩り+オーガニック野菜の収穫
+ヤギとふれあい」というプランで
年2回の体験研修に来られました。
(13)春休みにヤギ飼育体験 (広島市より)
子ども達がヤギを飼ってみたいと両
親を説得,3回もやって来ました。
飼育が無理なら春休みを利用してヤ
ギを飼うことで許可!ご両親も飼っ
てみると情が入り,ヤギを返す日は,
とってもさみしそうにしていました。
(14)地元の子ども達とつながる (町内の小学生の男の子・女の子)
牧場を始めてまず一番に,子ども達
が遊びに!優しい心で受け入れ,休
日はヤギの餌やり,子ヤギの授乳な
ど世話をしてくれます。ミニヤギ牧
場が子ども達が安心できる秘密基地
になっています。
(15)広域的に農家の方とつながる(今治農業女子,レモン,ブルーベリー,養鶏)
島に橋がかかり,豊浜町から大長レ
モンづくり名人の方にみかん・レモ
ン栽培の技術指導,ヤギ支援を。ま
た,豊浜町のイベントにはヤギと友
情出演しました。今治市農業女子の
みなさんが視察研修に来られました。
(16)地域おこしとヤギ活用 (今治市宮窪町地域おこし協力隊)
今治市宮窪町で地域の活性化を考え,
ヤギを活用した地域おこしに取り組
んでいる若者たち。ヤギが「希少家
畜」となった今,ヤギが町の特色を
引き出す新たなキーワードになると
思います。新しい発想と行動力で!
(17)ヤギ&農園の見学でつながる (リピーター,ヤギファン増加)
ネットや広報紙,新聞,イベントな
どでミニヤギに興味を持たれた方が
牧場に。愛らしく親しみやすいヤギ
を見て帰り際に,「幸せな時間を過ご
させていただきました」とおっしゃる。
私もヤギ飼ってよかったなぁと思う。
(18) 企業・自衛隊などからエコ除草 (中国電力新変電所;呉海上自衛隊)
海上自衛隊,中国電力よりオファが
あり,エコ除草を引き受ける。また,
緑地維持管理会社や太陽光発電の会
社など企業よりレンタルやヤギを利
用した事業の問い合わせ,牧場の視
察に来られています。
(19)「呉市動物愛護のつどい」 (呉市動物愛護センター)
動物愛護センターよりミニヤギとふ
れあいのイベント依頼。犬や猫など
の愛護と適正な使用に関心と理解を
持っていただけるようヤギも協力参
加。その後,その参加者の方が何度
もヤギ牧場の見学に来られます。
(20)ミニヤギの譲渡でつながる
鳥取県米子市,大阪府吹田市の幼稚
園,山口県下関市の寺院,高知県,
高松市など,広く県外からも子ヤギ
を飼いたい要望があります。遠くは
秋田県からも譲渡の依頼があります。
(21)地力維持にヤギの堆厩肥(たいきゅうひ)
窒素の揮散を防ぐのに過リン酸石灰をふ
りかけ,少し水を加えて踏み込み,積み
重ね雨よけのシートをかけます。2週間
後に切り返しをしてから肥料袋へ。
(22)援農サポーター (町外/ベトナム/フィリピンより)
援農サポーターとみかん園の整備,収穫
苗木を植えたり,ツリーハウスを作った
り等の活動をしています。みんなが憩い,
楽しく農的体験ができて学べるコミュニ
ケーションの場にしたいと願っています。
(23)除角・去勢・削蹄/種付けの支援
依頼があれば,除角や去勢,削蹄にでか
けています。種付けは,専用の小屋を建
て,安全第一を考えてペアリングの支援
をしています。
(24)ヤギの授乳体験
子ども達に子ヤギにミルクを与える体験
をしています。初めてでドキドキだった
のが全部飲み終わったらヤギに親近感が
わいてきます。
(25)職場の仲間・お母さん(ヤギと竹の子掘り/ヤギと栗拾い/ヤギとみかん狩)
近くに動物のふれあいや果物収穫体験が
できる場所はないか若いお母さんたちが
ネットで探して,お子さんにいろいろな
体験をさせたいと牧場に来られます。
(26)ヤギと竹林整備
ヤギは枯れ葉や雑木,竹の葉を食べてく
れるのでいっしょに竹林を整備します。
一人での作業が続きますが,時々メェー
と鳴くと,ほっと安心できます。
11 ヤギの可能性に着目した地域の活性化
ヤギを通して私は「人のつながりの連鎖」やこれまで経験したことがない出来事がた
くさんありました。ここでは,ヤギの可能性について考えてみたいと思います。
① ヤギが地域活性化の起爆剤に
ヤギの飼育目的には,除草利用および乳生産が多く,次いで伴侶動物としての利用
や教育利用および肉生産があげられます。しかしそれ以外にも,動物の可能性に着目
した地域活性化の取り組みがあります。
例えば,貧乏電車を救った和歌山県の猫の駅長(たま)。これは,「猫
達を駅の中に住まわせてもらえないか」という相談から「たま」を
駅長にするというアイディアでした。アイディアも斬新ですがそれ
を実行に移すところがすごいです。
また,ネットで繋がる情報が昔のイメージから新しい観光資源と
して注目を集めている例もあります。瀬戸内海のウサギ島(広島県
大久野島)は,島を訪れた観光客が「facebook」や「twitter」といっ
た SNS を使い,ウサギと撮った写真をネットにアップしてその情報
が拡散し,大久野島の知名度をどんどん上げていきました。戦時に
毒ガスを製造していた工場があったために,島が地図から姿を消さ
れてた暗い歴史のある大久野島は今,野生のウサギと SNS の力で「愛
らしい島」として竹原市の観光資源として盛り上がっています。
また,温泉に浸かるスノーモンキー(長野県山ノ内町)。これは,
「地獄谷野猿公苑」の職員が撮影した 1 枚の写真がアメリカの自然
写真コンテスト「ネイチャーズ・ベスト国際写真コンテスト 2006」
でグランプリを受賞したことがきっかけで日本の「SNOW MONKEY」
が外国人の間で大人気になり,冬でも多くの外国人が訪れています。
他にも,「世界の猫島」となった香川県の男木島。猫たちの癒しの
写真が口コミで,日本だけではなく世界にも広がり有名になりアメリカ
や香港など世界各国から観光客が訪れています。そのほかに,奈良
や安芸の宮島のシカの例など,たくさんあります。
ヤギのいる風景は,新たな観光資源になると思います。YouTube
で多く再生されるのは,「動物」関連動画が人気のジャンルです。
今やプログやサイト,YouTube等のメディアは私たちの身近にあ
り,興味を多く引きつけることができれば「大きな影響力」を持ち,
それをうまく利用すれば観光業など,他の分野でも良い影響力が生
まれてくると思います。
そのほかに,広島県の米農家の方が「ヤギと育てた安心なお米」と
パソコンでラベルを作成して販売後,お米のイメージがアップして
販売が好調です。
このように,手作りの商品や農作物の広告でもヤギを利用(マス
コット)することができます。
動物は,地域の観光や広告,人と人を繋ぐコミュニケーションツ
ールやこころの癒し,人の心を動かすメディアとして機能します。
発想を変えれば,ヤギが地域活性化の起爆剤になると思います。
② 有畜複合農業の可能性
かつて,その土地独自の風土に支えられて作物を育て作物の残り物や生物の排泄物
は大地に返り,物質の循環と再生産が行われてきました。循環型農業の取り組みでは,
沖縄や奄美大島で,ヤギ飼育と果樹生産+ヤギの堆肥を組み合わせた有機栽培に取り
組み,堆肥化したやぎ糞を施用することで味が良くなり,大きなバナナやスモモ,み
かん類を生産している方がいらっしゃいます。
③ 教育における体験活動の可能性
いのちの教育,また生命を理解するための体験的な
学習の必要性は高まっています。生命教育(生命を尊
ぶ態度の育成)は,平成18 年に改正された教育基本
法で教育の5つの目的のうちひとつとして謳われてい
ます(第二条の四)。また,新学習指導要領において
も,「道徳教育」では,生命を尊重する態度を養うこと,
小学校「生活科」においては「飼育栽培」が2年間に
わたる学習内容として記載される等,学校教育におい
て生命とのふれあいを継続的に見守る活動の必要性が高まっています。さらに,「理科」
の学習では,体験的・実験的な自然事象の理解が明確に推奨されるようになってきて
います。このように,授業で「生命理解教育」を取り扱う場面が増えています。
しかし,学校では動物の取り扱いについての知識が十分でなく,動物飼育自体が完
全に否定されてしまったり,飼育動物がいても教材として十分な活用が行われない現
状があります。
ミニヤギ牧場では,これまでに小学校の生活科,小・中学校の総合的な学習におい
てヤギを連れて出前授業を行ったり,みかん狩り+牧場の社会見学の依頼を引き受け
てきました。その後,関わった子ども達の祖父や祖母,家族ぐるみで牧場見学に来ら
れる人が増えています。
④新たな発想で地域を元気に
ヤギは除草,学校教育,アニマルセラピーあるいは地域のイメージ作りや商品の広
告,観光など,多面的機能があります。ヤギの利用目的ばかりにこだわらないでくだ
さい。可能性に着目すれば,多様にあると思います。
愚痴や国を批判することにとどまっている限り,何か新しい動きの立ち上がりもな
いし,問題の解決にもならないと思います。「ないものは自分たちでつくる」という発
想もあると思います。
例えば,ヤギは英語でGoat(ゴート)なので,5月10日(それに近い休日)を「宮
窪ヤギの日」として,小規模で良いので声をかけ合って地域で育てているヤギを集め,
有志が集まってヤギとのふれあい,写生大会や写真コンテスト,地元で作られるもの,
新たな特産品(パン,ヤギクッキー)などを持ち寄って販売する等の企画が考えられ
ます。小規模で良いので,「ヤギの日」をキーワードにして,地域の方々や仲間と一緒
になって考えて行動すればできると思います。
新しい変化というのは,最初は一部の小さな実践から始まります。最終的には地域
内・組織内で理解され,多くの人へ広がっていきます。できることから少しずつやっ
ていこうと決めて行動すれば,小さな一歩でも必ず前に進めることができます。
終わりに A reason for living (生きがい) -日常の中に小さな喜びを-
心 →やすらぎや優しさをもたらしてくれるヤギ
時間 →話し相手や遊び相手になってくれるヤギ
空間 →日々の生活にほのぼのとした温かさを醸し出してくれるヤギ
ヤギは,心と時間と空間のすき間を埋めてくれる存在です。
「ふるさと再生ヤギプロジェクト」を始めてから,様々な人
との出会いがありました。ヤギと始まる新たな物語です。
ふれあいイベント,レンタルや譲渡を通して,県内外の多
くの方の素敵な笑顔をたくさん見てきました。何より私自
身の心が癒されました。
ささやかな取り組みですが,ヤギの飼育やヤギを利用し
た除草が口コミやインターネットで広がり,相談や問い合
わせが多くなりました。
牧場を始めた1年目は,「この島にヤギの牧場はあるん
かいのぉ…?」と答えておられた地域の方々が,ミニヤギ
牧場へ町内外からたくさんの人が集まり,この島でミニヤ
ギを飼っていることが知られるようになってきました。
今では,牧場のある場所を聞きに来た人へ「菅原先生の
所かいの?教えてあげよう。ついてきんさい。」と進んで案内してくださる方が増え,
ヤギを飼うことへの理解と応援をしてくださるようになりました。
やっぱり地域の方はちゃんと見ているのですね。少しずつですが,下蒲刈町が「ミ
ニヤギのいる島」になったのかな?と思っています。
「ふるさと再生」は,『温故知新』。故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知れば未来の
かてとなるという発想です。
私の好きな格言に,「巧詐は 拙誠に如かず」(韓非子)があります。これからも,つ
こ う さ せつ せい し
たない取り組みですが,ヤギの生態,習性(行動),生理に関する知識の習得に努め,
誠実に,地域の風土に根ざした暮らし・農業を守り,ふるさとが自慢できる取り組み
をしていきたいと思います。ホーム / 写真 / ライフスタイル / Mouni Roy は、オレンジ色のアンサンブルで神秘的な女王として着飾っています. 内部の写真
Mouni Roy は、オレンジ色のアンサンブルでミスティック クイーンとして着飾っています。内部の写真

Mouni Roy は、私たちにファッションの目標を与え続けています。彼女のドゥルガ プージャ ファッション ダイアリーであれ、ガウンやパンツスーツで百万ドルのように見える. モウニの仕立て屋のファッションセンスは、すべての人に愛され、慕われています。俳優は、ある日、明るいオレンジ色のアンサンブルで着飾り、相変わらず見事に見える彼女自身のたくさんの写真の形で私たちに新鮮なファッションのインスピレーションを与えました. (Instagram / @imouniroy)

モウニはファッション デザイナー ハウス Deme のミューズを演じ、デザイナー ハウスの棚から明るいオレンジ色の服を選びました (Instagram/@imouniroy)。

モウニは、ネックラインが大きく開いたスリップ オレンジのブラウスを着て、長く流れるようなオレンジのサテン スカートを合わせました。ブラウスからくるぶしまでのトレーンもポイントに。 (Instagram/@imouniroy)

ここでは、真っ白なビキニセットを着てプールでくつろぐモウニの姿が見られる。彼女は、このクリックと最小限のメイクアップのために、髪の毛を開いたままにしました. (Instagram / @imouniroy)

モウニの写真についてどう思いますか。荷物をまとめて、ビーチや山での休暇に出かける動機になりましたか? (Instagram/@imouniroy)
タイからエジプトまで: 予算に優しい海外旅行先トップ 6

海外で休暇を過ごすことは誰もが抱く願望かもしれませんが、その費用は往々にして圧倒的なものになります。心配しないで; インドから利用できる手頃な価格の国際旅行オプションがたくさんあります。旅全体を綿密に計画すれば、財布に穴を空けることなく、海外旅行に簡単に乗り出すことができます.(Unsplash)
インドの隣国の 1 つであるスリランカは、さまざまな文化、快適な気温、ジャングルや乾燥した平野から高地や砂浜に至るまでの風景で知られています。1人あたりの価格はRsの間です。35,000 と 40,000 (ピクセル)





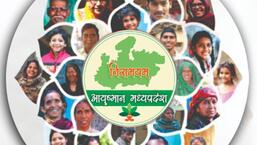
コメント
コメントを投稿