世界塩の旅
「世界塩の旅」という題で前に書いたり話をしたことがある。
自分自身でスナップしたり見聞きしたことを主に、コレクションのスライドを上映して。
この「世界塩の旅」はその映像の記録を残しておこうとするものである。全部とはいかないにしても若干の糸口になろうかと纏めたものである。
「
食塩と健康」(第一出版)には文を書き文献を示したが、その中では示されなかった「image」を記録としてここに纏めた。私の撮影したもののほか、他の方の作品の「引用」もあるが、それぞれ出所があり、その総てが記載されていないことのお許しを願う。
日本の特に東北地方の脳卒中や高血圧の予防を目標に疫学的研究を展開し、「食塩摂取」の実情にふれ、検討でき、食塩過剰摂取の疾病発生論的意義を考えていた。幸い文部省の在外研究の機会に恵まれ、1965年から1966年にかけてアメリカのミネソタ大学に滞在することができた。この時世界的規模で食塩摂取と各種人口集団の血圧の水準と分布についての資料を検討し両者の関連についての考え方についての「作業仮説」をセミナ-で発表した。
そのあとヨ-ロッパにも回る経験をもつことができた。
その後数回のアメリカ・ヨ-ロッパへの学会出席の途次見聞を広めることができた。
1970年ロンドンでの第6回世界心臓学会で
「Causative factor in hypertension」の円卓会議(round-table-session)で
私なりの「Salt Factor」についての考え方を述べる機会が与えられた。
ロンドンにて
「しかし私にはロンドン塔(The Tower)の宝物殿に入ったときの、そこにあるものをみたときの、おどろき、感激は忘れられない。
それは代々伝わる即位用の王冠や王笏ではない。大きなダイヤモンドが入った王冠ではない。
それらの宝物の一番上におかれていた金色にかがやく”塩の入れ物”(Salt Cellar)であったのだ。説明の文面をよくよんでいくうちに”Salt”という字が私の目にとびこんできたときには、自分の目を疑った」

The Salt Cellar
アメリカにて
アメリカにいた富永祐民君からワシントンの家で食塩の倉庫を見てきた手紙を戴いていたので、昭和61年第10回世界心臓病学会がワシントンであったとき、観光船にのって見に行った。
昔の倉庫に”Salthouse”があった。
博物館には”Silver Salt Stand””Salt Dish””Salt Spoon”がかざられていた。
久米清治さんをサクラメントへ訪ねたときも 塩の倉庫や昔の食事のメニュ-が歴史館にあった。
アメリカは200年前ヨ-ロッパからの移民によって発展していった国であったので、食塩は現地で求めるというより、船によって本国から運ばれたようにみえた。
”Salt Lake City”は文字通り”塩の湖”であった。
モルモン教会・オルガンなど見たあと、湖へ向かった。皆湖の水の味見をしていた。塩の結晶の資料があった。ここでは浮き袋がなくても浮きますという写真のついた「塩」のお土産(25セント)を買った。
Time誌(March15,1982)が「塩」の特集をやった。
日米の比較など、ミネソタで一緒だったHenryBlackburnらがコメントしていた。
題は「塩:新しい悪者?」であった。
Salt and Pepper
国際線にのって食事がでると きまって ”Salt and Pepper”がついてきた。
乗るたびに 講義に使おうと コレクションした 。
日航ではそのほかに醤油”soy sauce”がついていた。
”salt””pepper”と書いてあるのはすぐ分かるが アナが一つ三つと開いているだけのもあった。 三つのほうが食塩であった。 色の違うのは白は塩 茶はコショウであった。
ソ連の飛行機にのったら10年前と同じものであった。 またどのホテルへいっても同じ入れ物であった。
コペンハ-ゲンの例の人魚のある海岸を歩いているときだったか、お土産屋さんの店先に木製の入れ物があった。裏側をみたら”Salt”とあった。
ウイ-ンの美術館に塩にちなんだ置物があるとテレビで放映された。
noーsalt culture
Lowenstainの北ブラジルのアマゾン地帯に住む人々の血圧に関する報告(Lancet,1,389,1961.)を見ていたので、食塩との関係で私の作業仮説の例に入れていたが、南米には行く機会はなかった。
1975年になってOliverらによって”Yanomama Indian”(綴りは色々で、読み方も色々であり、わが国ではヤノマモ・ヤノママ・ヤノマミなどといわれている)の”no-salt”cultureの報告がでた。学会報告もあり、テレビにも紹介されることになった。
アフリカに子供をつれて行って人類生態学の研究をされていた田中二郎先生(砂漠の狩人:中央新書,1978.)が弘前大学におられた頃、「濾紙法」で尿中のNa、Kを調べ報告(日本医事新報,3269,,25-27,昭60)したことがあった。このブシュマンの対象も”no-salt”cultureにある人々であった。
東大の鈴木継美・大塚柳太郎先生らのパプア・ニュ-ギニヤにおlける人類生態学研究に協力して、食塩摂取について考察する機会があった。
竹森幸一君らの「濾紙法」「毛髪」の検討もできた。
私は現地調査には参加出来なかったが、論文報告またTVなどニュ-ギニヤの写真など多く勉強することができた。本多勝一氏の紀行記など
塩の花があり、それを焼いて塩を造り、天井につるしているとあった。
テレビの世界ふしぎ発見にも「塩の問題」がでたことがあった。
ダニ族の例、ラニ族に繁栄をもたらしたものは何かであった。
この時の説明は「塩水の泉」であった。
パプアニュ-ギニヤの「塩」の成分は報告によると、NaClよりKClが主であった。
2002年10月世界不思議発見のテレビで、パプアニュ-ギニヤのワナカパリ村アンガ族で「いも」に「塩」をかけて食べているところ、草をもやしてその灰から塩を造っているところが放映されていた
「生肉を食べる人」といわれたエスキモ-(差別語をさけて最近はイヌイットといわれる)は
ド-ル先生の論文には食塩5グラム以下と報告され、本多勝一氏の紀行記にも 「味付けのない食事への試練」が書かれていた。
住の温度環境は日本の東北地方より良いと思われるが、天然の冷蔵庫の中に生活するエスキモ-の人々は食物を「塩蔵」する必要はなかった。
動物が人間の尿をあさっている風景が放映されたことがあった。
オ-ストラリヤの大陸に住む原住民も”no-salt”であるといわれる。
論文もあり、オ-ストラリヤ放送の番組制作で食塩の取材に弘前へきたこともあった。
塩のある世界
歴史を記載したヘロドトスについてのテレビ番組にエジプトのデルタ地帯の「塩湖」が放映された。「ナトリウム」の語源がこの湖の名前に由来するという説明であった。
「
聖書にみる塩」に書いたように、旧約聖書の世界では、「塩の海」にかかわる記載が多い。
地球を空からみると「死海」のように塩に覆われて白い湖にみえるところがあるようである。
南米・オ-ストラリヤ・中国・モンゴルなどなど
こういうところでは塩をただかき集めればよい。
サハラ砂漠の塩
2004年2月テ世界不思議発見のテレビでサハラ砂漠に「塩の湖」があると放映されていた
2003年8月テレビ「極限への旅」(Going to extreams)「世界一のあつさエチオピア」の中で、「塩」をとりにらくだの旅が放映された。
世界まるごとHowMuchの番組に塩の問題が出たことがたった。
製塩法は世界各地で人間の知恵によって色々考えられてきた。
塩は塩蔵に用いられた歴史がある。
南米での塩づくりのテレビの放映があった。
南米インカ帝国の山に段々畑があって何の食料をつくっているかという問題がでた。正解は「塩」で、山の岩塩をとかした水を下へ下へと濃くして塩をつくるのであると解説があった。
南米アンデスの不思議な湖の放映(20041204)があった
南米チリ-(TV20060121)のアンデスにラグ-ナ・ベルゲ(緑の湖)があり
そこには「塩の結晶」がみられたと
 | <form action="http://www.kunpfukai.com/imai_naika/report/"> <select name="list"> <option selected="selected" value="">▼新着情報 項目を選択してから『GOボタン』を押してください </option> <option value="medical/diary15.html"> |-アメリカの医療費 「かかりつけ医通信」より </option> </select> <input name="BUTTON" type="BUTTON" value="GO" /> </form> |
| |
|
お問い合わせ いまい内科クリニック
〒665-0021 宝塚市中州2丁目1-28 TEL 0797-76-5177  | | |
 第11回のリサナメント「現代の長寿食」 第11回のリサナメント「現代の長寿食」  「ついに突きとめた究極の長寿食
付、簡単に作れる長寿食レシピ 洋泉社 家森幸男著 720円」 「人は血管とともに老いる。」
家森教授
高血圧ラット(SHR、SHR-sp)の開発者。
脳卒中ラット、生後25週目までに100%脳卒中をおこす。
脳卒中を起こす遺伝子、、この遺伝子は食べ物やストレスに反応しやすい。
脳卒中ラットに、1%の食塩水を飲ませると、100日以内に脳卒中を起こし全滅する。
+大豆タンパク 寿命は2倍;+カルシウム 寿命は2倍+マグネシウム 寿命は5倍
1985年から、18年間 世界25ヶ国、 60地域 のべ10,000人を調査した結果:
現代の長寿食の共通点は、、
① 魚や肉をバランスよく、しかも内臓まで食べる。
② 大豆などの豆類やナッツ類を摂る。
③ 野菜、くだものなどをたっぷり食べて、海藻も利用する。
④ 乳製品を積極的に摂る。
⑤ 動物性脂肪は摂り過ぎない。
⑥ 塩分を制限する。
三大成人病 がん、(♂長野 ♀沖縄) 脳卒中、心臓病(♂沖縄 ♀沖縄)
塩分摂取と 胃がん、脳卒中の発生
沖縄 塩分摂取 一日8g 胃がんの発生率が少ない。
高血圧 マサイ ⇒ チベット(18g)
肥満↑、カルシウム マグネシウム↓
脳卒中は 食塩摂取が少ないほど少なく。コレステロールはほどほど:180mg/dl
心筋梗塞 飽和脂肪酸が多いほどリスク↑、不飽和脂肪酸を摂取、(EPA、DHA)リスク ↓
タウリン(魚に含まれるアミノ酸): 一日、魚100g(切り身1枚)、週に4日。
沖縄の長寿は、環境か遺伝か >> 環境!(肥満)
沖縄、ハワイ、ブラジル
ハブともにコレステロールが高い。
肉食⇒心臓病はブラジルに一番多い。魚の摂取量が少ない!
肉食など脂肪の摂取が進むと、糖尿病↑ 日本人は脂肪の摂取に弱い。
沖縄県の伝統食とは
① 米を主食にして、脂肪の摂取が少ない。(50-60%が炭水化物→ 先進国では稀なこと)
② タウリンなどの魚に多いアミノ酸が高血圧、動脈硬化を防ぐ
③ Fish oil (不飽和脂肪酸 EPA DHA)
④ 海藻 などの食物繊維 マグネシウム 銅
⑤ 大豆食 良質のタンパク質 食物繊維 カリウム ミネラル イソフラボン
日本食の欠点
① 塩分が多い。
② 和食は一般にタンパク質の摂取が少ない(沖縄は例外的に豚肉↑)
③ 乳製品の摂取が少なく、カルシウムの摂取が少ない。
④ 野菜や果物などの食物繊維、抗酸化作用のある緑黄色野菜の摂取が少ない。
世界一魚の摂取が多いのは、富山県。
ただし、塩分摂取は沖縄の倍。胃がんも多い。
島根県内では、
隠岐 >> 山村
いかを丸ごと。わかめ。野菜も豊富。
ネパール 50歳代の半数が高血圧。
タウリンを一日3g補うと、高血圧が治る。
タウリンの摂取が多いと、心臓病は少ない。
ブラジル カンポグランデ シエラスコ(焼肉)肥満 高血圧
ここに移住した沖縄人は、17年も平均寿命が短い。
ニューファンドランド 塩漬け 油で揚げる調理法。
魚を食べるだけではなく、かならず野菜を併用。
カリウムや植物繊維で、塩やコレステロールの害を防ぐ
大豆:
大豆タンパクにより、コレステロールを腸管内で処理する。
イソフラボンがNOを増やす。
イソフラボン;前立腺がん 乳がんを抑える。(米国の脂肪多い食生活では、乳がん、前立腺がんの発症率が高い。)
沖縄名護の女性、イソフラボン摂取世界一 乳がんの死亡率も一番少ない。
アメリカFDAも、一日25gの大豆を摂って、コレステロールの低い食事をすれば、 動脈硬化から心筋梗塞になるのを防ぐことができる。
高齢社会の抱える問題:「寝たきり」 「痴呆」
マサイ族 ミルクの多飲(一日3リットルから10リットル)
タンザニアでは、マサイと違ってミルクを飲む習慣は全くないが、骨密度は世界一。
枝豆の摂取量が多い。重いものを運ぶ習慣。
枝豆を乾燥して保存。
一般に野菜や果物を乾燥して保存し、常食する地域は長寿。
中国 貴陽 中国有数の長寿地域 高原にある 稲作不向き
トウモロコシと大豆 石灰岩 ミネラルの多い水
醤油、味噌 豆腐 油揚げ 納豆 大豆の徹底利用。
大豆はマメの中でもとりわけタンパク質を多く含有。
大豆の摂取の多い地域では、生活習慣病 とくに心臓病が少ない。
尿中イソフラボンの摂取の多い地域ほど、心筋梗塞は少ない。
梅県 客家 漢民族の末裔 勤勉な生活 塩辛い味付けを好むのに比較的長命。
米食を中心に バランスよく
醸豆腐(ニャンドウフ 豆腐の中に豚肉をつめる)
内臓の利用、髙繊維食 大根の葉を粉末にして団子 漬物としては保存しない
豊富な果物 果物のカリウムはナトリウムの害を打ち消す。
台湾
醸豆腐 豆漿をドンブリで
お粥 豊富な果物 抗酸化作用をもつお茶(カテキン)
台湾での脳卒中は軽症の人が多い。
タンパク質が日本人より豊富 塩分摂取は10g(日本人13g)
野菜は動脈硬化を予防する。
食物繊維 カリウム 抗酸化栄養素 などが含まれている。
とくに食物繊維はコレステロールや糖分を吸着して、排泄する、、高脂血症や糖尿病の予防。便通を促して大腸がんの予防にも有効。
西日本 沖縄 隠岐 愛媛(トウモロコシのあらびき;食物繊維、銅、亜鉛などのミネラルカリウム)
グルジア
プルーンの発祥
肉類、鶏肉などは煮でたり蒸したりして、脂を抜いてある。
ヨーグルトをどんぶりに1杯(乳酸菌が腸の調子を整え、消化吸収を助け、免疫力も増強する)
赤ワイン( フレンチ パラドックス )
ブドウなどの果実も、種も皮も食べる。
エクアドル ピルカバンバ コーカサス、フンザ に並んで世界3大長寿
赤道直下 海抜1500m 豊富な果物 クイのフライ
トウモロコシ ユッカといういも
ケソという(豆腐のような)チーズ ケソのスープ。
冷蔵庫がないので肉を保存することができない。
長寿国では、牛乳、ヨーグルト、チーズなどを上手に摂っている。
長寿のための、肉の食べ方。
「タンパク質は摂るが、脂は落として食べる」
しゃぶしゃぶ、焼き鳥、カリカリベーコン
塩は極力使わず、香辛料で食べる。
沖縄の食事
① 豚肉をよく食べる。煮込んで脂を充分落とす。トンソクなど。長生きのヒトには肉好きが多い。臓物まで食べる。
② 昆布の使用量が多い。
③ 魚も刺身でよく食べる。
④ 豆腐も毎食食べる。
⑤ ゆいまーる という、寄り合い。
沖縄の豚肉の食べ方と、同じ食べ方を、グルジアで見かける。
ウイグルとアルタイ
ウイグルでは、ボローという炊き込みご飯。
アルタイは、遊牧民。野菜をとらない。
一日の塩分摂取を6g(WHO推奨)まで減らせば、平均寿命が3年延びる。
家 森 家 の 献 立 ① 朝、昼、夕の総摂取カロリーは、1800カロリー
② 朝、昼、夕の三食で、30品目の食材。
③ 塩、油、砂糖は控えめに。
五目味噌汁(味噌の量は半分に、にんじん、ごぼうなどの根野菜を多く。)
だしの、こんぶやいりこも食べる。
味噌を控えて、ごまを使う。
きなこヨーグルト
動物性たんぱくのヨーグルトと、植物性たんぱくのきな粉の組み合わせ。
魚料理
煮魚は薄味に、焼き魚には塩を振らずに、レモン、カボス、おろし生姜などを使う。
砂糖は黒砂糖
お豆腐 しょうゆを使わず、ねぎ、かつを節、生姜などの薬味で。
魚貝と野菜たっぷりのスープ。
揚げ物、甘いものは控えて。
緑茶は一日、3杯。 | BACK | |
| |
お問い合わせ いまい内科クリニック
〒665-0021 宝塚市中州2丁目1-28 TEL 0797-76-5177 広島に恋するみさきダイアリー八幡 美咲 MISAKI YAHATA 食べること・旅をすることが大好きです! 広島の方々に信頼され愛されるアナウンサーを目指して頑張ります!! いろいろなジャンルに挑戦したいです。 人との出会いを大切に広島の魅力を深掘りしていきます♪ プロフィール| 自己紹介 | ■アナウンサーになって良かったこと、感動したこと、辛かったこと
・たくさんの人の想いが詰まった情報を多くの人に届けられること。
・頑張っている人を取材しその思いを伝えられること。
普段、なかなか会えない人に会えること。(昨年行われたラグビーワールドカップでは
フランス代表やウェールズ代表選手たちに直接取材しました)
同じ日が1日としてなく発見と失敗の毎日です。
人としてもアナウンサーとしても尊敬する先輩方のもとで日々成長していきたいです。
■資格、免許
英語検定2級・漢字検定2級 英会話
JCS オープンダイバー資格・自動車免許
■趣味
スポーツ観戦 旅行(世界14か国旅しました)
映画鑑賞 カラオケ 写真撮影
■特技
どこでも3秒で寝られる/決断や切りかえが早い
子どもと仲良くなること(一番下の妹が9歳です。)
ポジティブ思考 体が柔らかい チアダンス 鉄棒
■ストレス解消法
甘いものを食べる。中でもアイスが大好き
■好きな食べ物
甘栗・かぼちゃ・アイス・おっぱいチーズケーキ・いちご・卵かけごはん・納豆
■今、一番ほしいもの
肩がこらない肩・日焼けしない肌
■将来、行ってみたい場所
カンクン モルディブ 世界一周
■好きな言葉
神様は越えられない壁を与えない 必要なときに必要なことが起こる
■好きな映画
focus あと1センチの恋
■好みの異性のタイプ
なにかに一生懸命打ち込んでいる人
■今後の目標
ニュースをわかりやすくしっかり伝えられるアナウンサー |
|---|
最近の投稿【サンフレ】荒木選手の試合前のルーティンに驚愕!収録で垣間見た選手たちの素顔 2021.02.01 【フットスタイル】2つの想いが込められた「俺たちの円陣プロジェクト」 2020.12.18 サンフレッチェ広島 21歳の守護神「大迫選手」 2020.12.04 最初で最後の夏 八幡美咲 2020.09.03
pagetop |
|
|
|
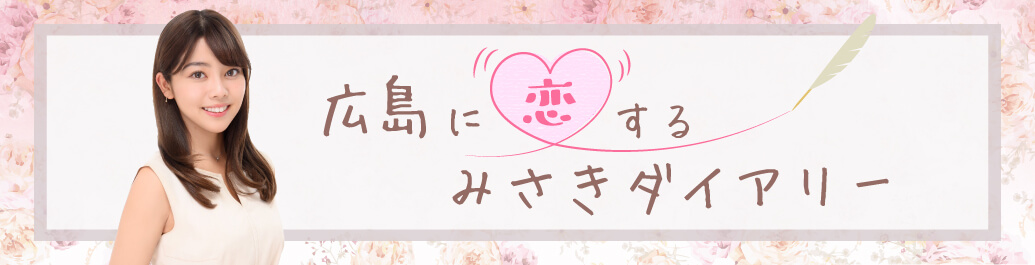
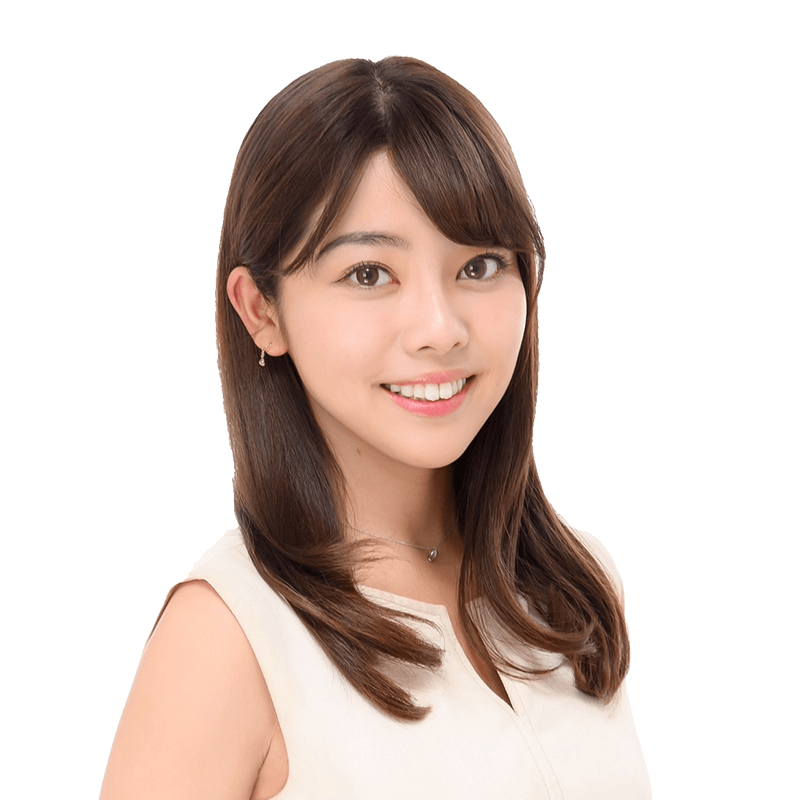








コメント
コメントを投稿