सूर्य की त्रिज्या लगभग 700,000 किमी और व्यास लगभग 1,400,000 किमी है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है।
広島大学長からのメッセージ

平成27年4月1日より浅原利正前学長の後任として、第12代広島大学長に就任しました。よろしくお願いします。 広島大学は「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し、「平和を希求する精神」「新たなる知の創造」「豊かな人間性を培う教育」「地域社会・国際社会との共存」「絶えざる自己変革」の5つの理念の下、11学部11研究科を擁する日本でも有数の総合研究大学として、大きく発展を遂げています。 平成26年度スーパーグローバル大学創成支援のタイプA(トップ型)13大学の1つに、中国四国地方で唯一採択されました。今後10年以内に教育力・研究力を両輪とした大学改革を推進しながら、グローバル人材を持続的に輩出し、知を創造する世界トップ100の大学を目指します。 現代社会は科学技術が目覚ましく進歩する一方で、自然災害の多発、貧富の差の拡大、頻発する地域紛争やテロなど多くの困難に直面しています。未知の問題に自ら立ち向かう「平和を希求する国際的教養人」の育成に全力を挙げて取り組みます。
第12代広島大学長 越智 光夫

式辞・挨拶など
Copyright © 2003- 広島大学




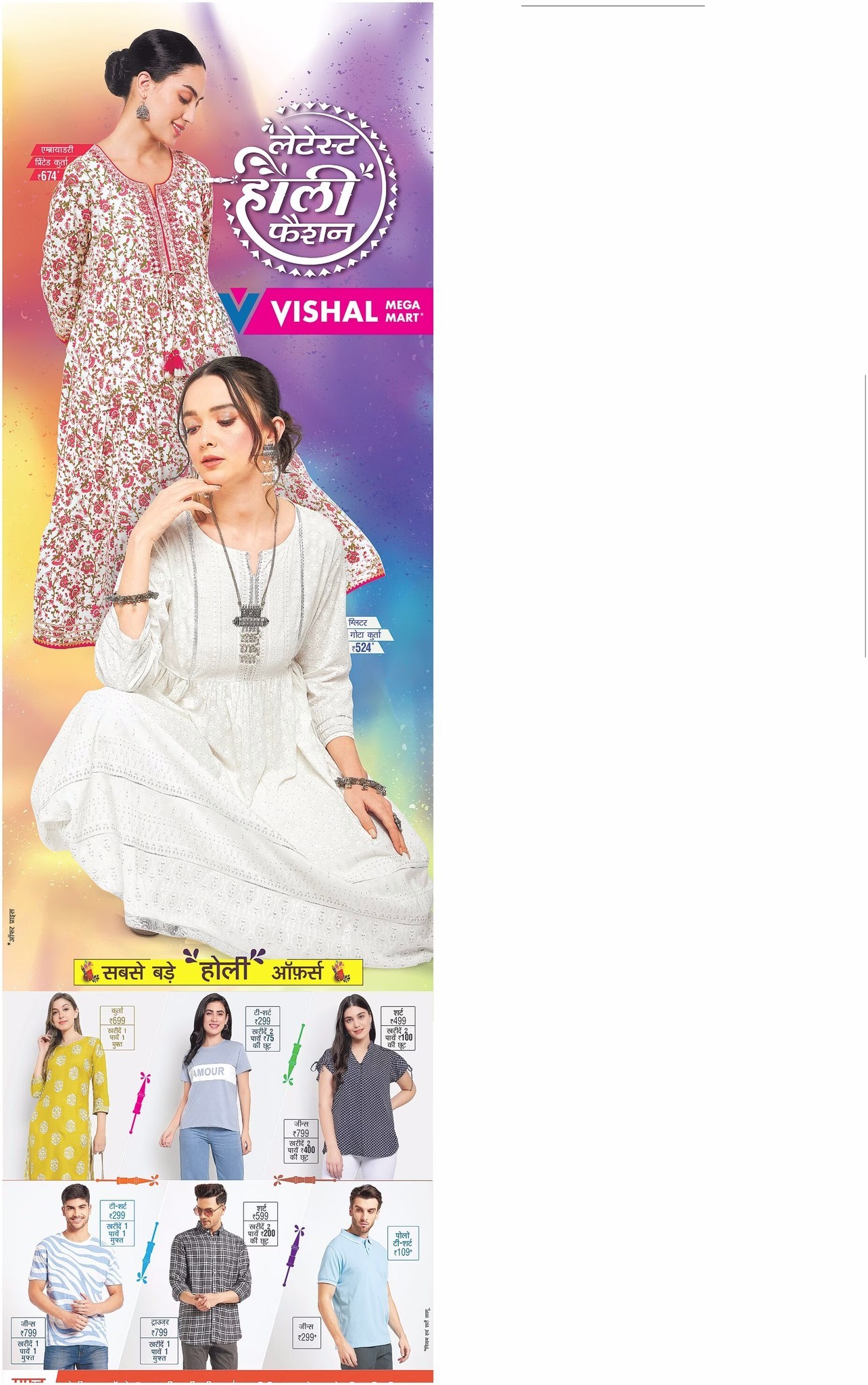
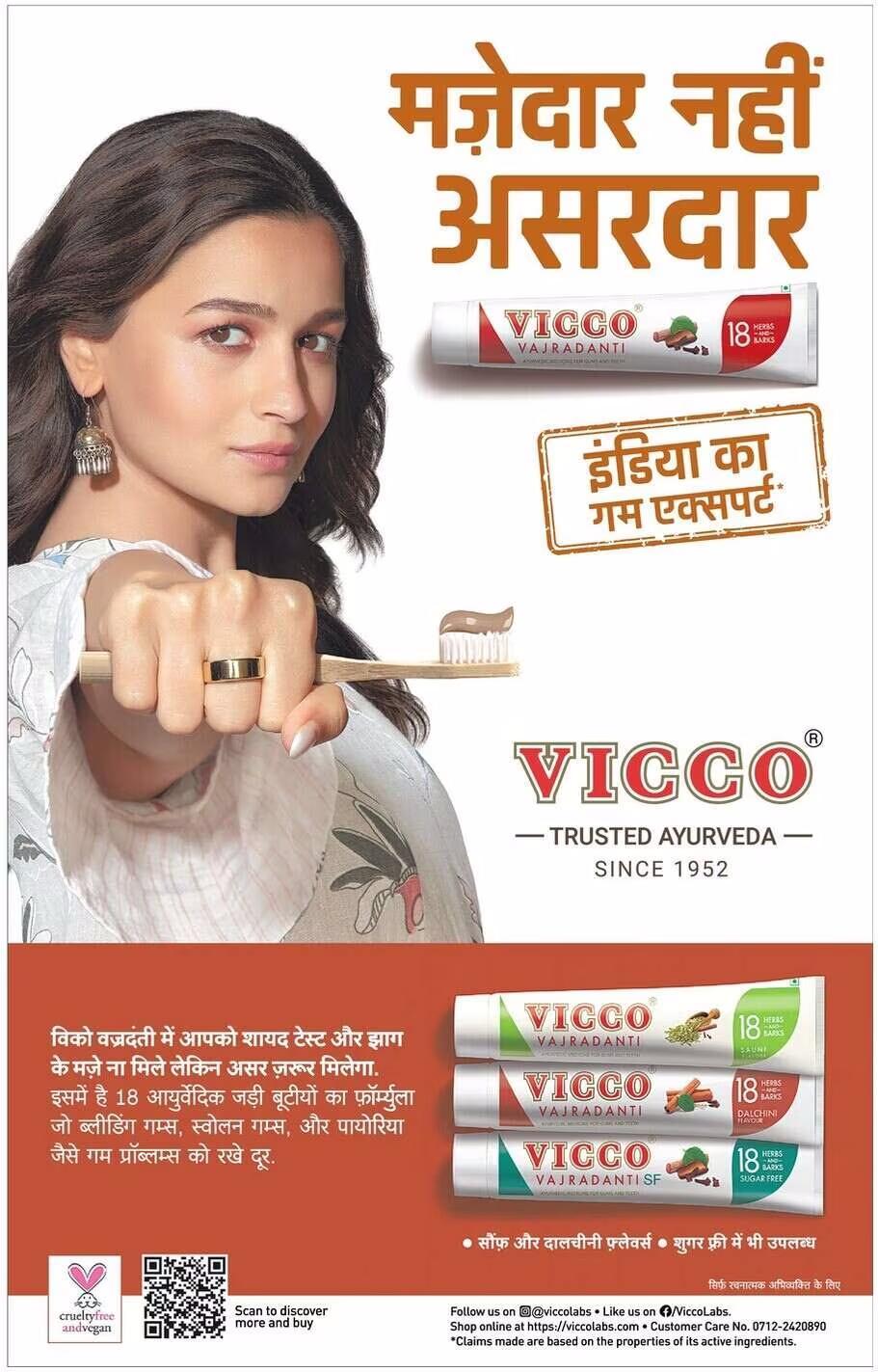


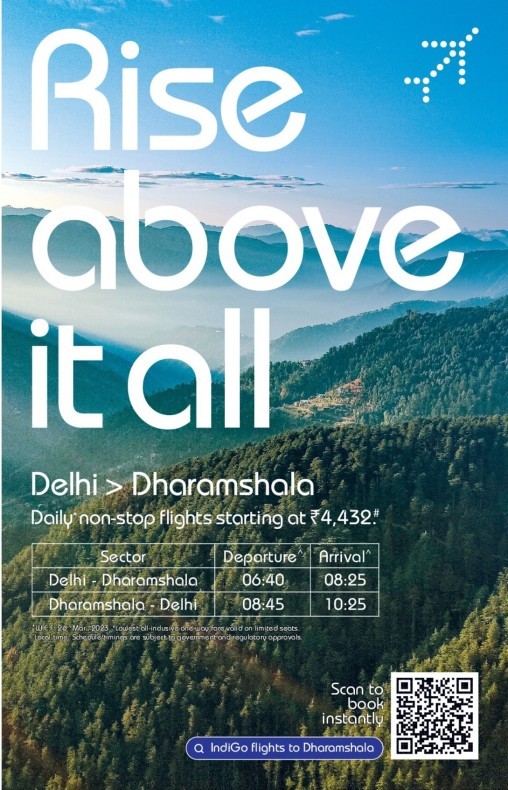
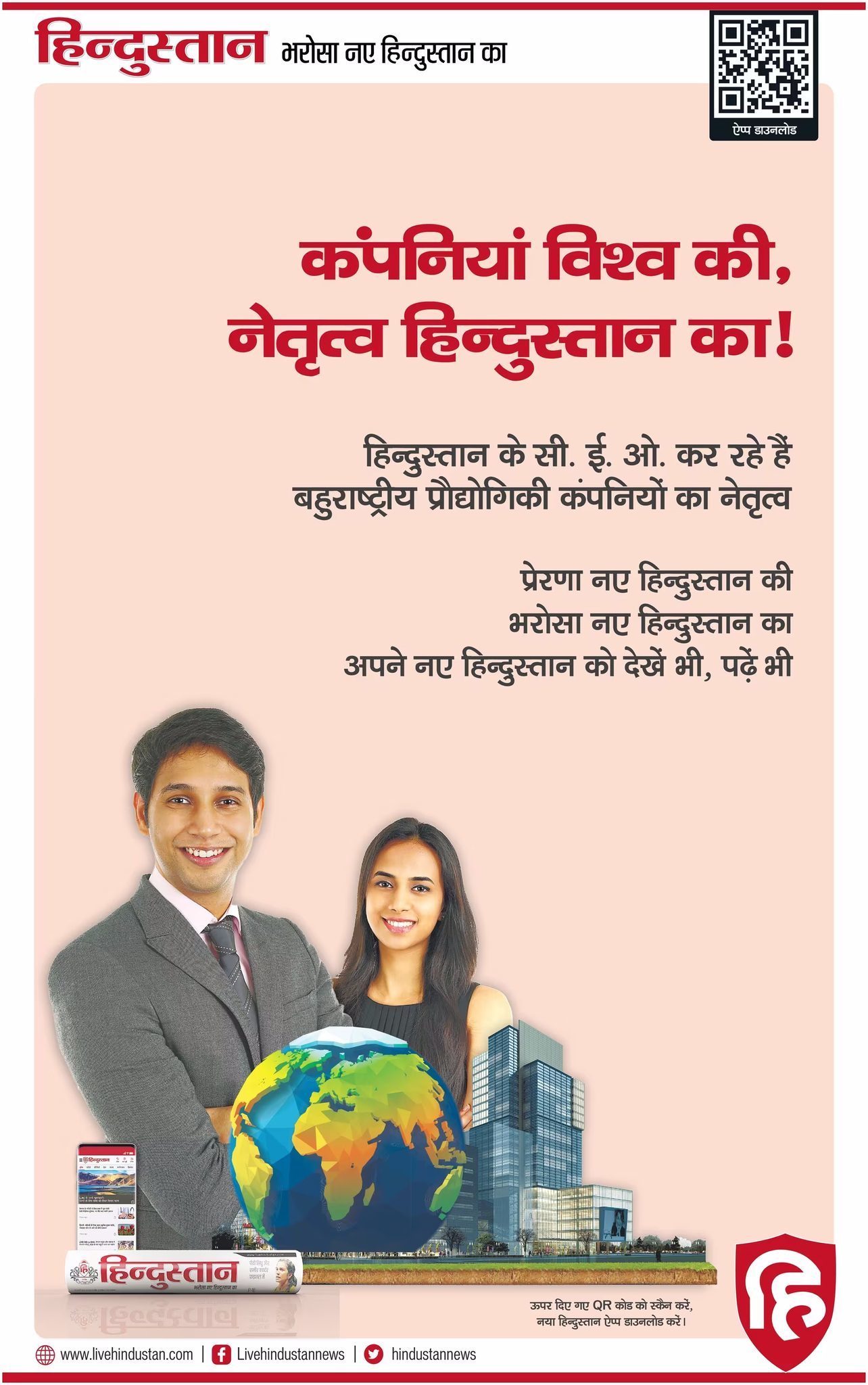
岩谷観音跡(いわやかんのんあと)


約700年前、甲斐国(現山梨県)は近藤三郎左衛門によって建立されたといいます。
多くの人の信仰を集め、初観音(旧暦の1月18日)には大きな祭り供養が行われ、多くの屋台も並び、また正月には多くの初詣客でにぎわったそうです。
観音堂の所在と補修・管理をめぐる争いが府中と温品(広島市東区温品町)の間であったのですが、後年、話し合いで観音堂は温品の地と決められました。
現在堂宇等は焼失し、高尾山に至る登山道の途中境内跡に石積遺構や石碑等が残るだけです。(本尊観世音菩薩は、現在は広島市東区の岩谷寺にあります)



続けて呉娑々宇山登山も可能です。
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
黄幡神社跡(おうばんじんじゃあと)・明神社跡(みょうじんじゃあと)
 記録がないため詳細は不明で明神社の意義も定かでないのですが、一名黄幡社と称することから八将神黄幡(軍神の守護神の一)を祀ったもので、のちに明神社と呼ぶようになったのではないかとも推測されます。
記録がないため詳細は不明で明神社の意義も定かでないのですが、一名黄幡社と称することから八将神黄幡(軍神の守護神の一)を祀ったもので、のちに明神社と呼ぶようになったのではないかとも推測されます。
明治44年(1911年)2月多家神社に合祀されました。
字尾首黄幡山の突端にあったものと思われており、団地造成により地形は一変したのですが、昭和46年(1971年)現在地に碑が建立されました。
正徳2年(1712年)の「府中村寺社堂古跡帖」に黄幡神の名が記されています。
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
ムクノキ跡
 樹高27.5メートル、胸高幹囲4.8メートルと県下有数の巨樹で、ひろしま県民文化100選(花と木100選 昭和62年)にも指定されていたムクノキは、平成3年(1991年)9月27日の台風19号によって主幹部分高3.5メートルを残し、倒壊しました。
樹高27.5メートル、胸高幹囲4.8メートルと県下有数の巨樹で、ひろしま県民文化100選(花と木100選 昭和62年)にも指定されていたムクノキは、平成3年(1991年)9月27日の台風19号によって主幹部分高3.5メートルを残し、倒壊しました。
その昔、船が沖から帰ってくるとき猿猴川の河口に近づくと、北方にはこのムクノキがよく見えたといいます。
現在、残っている主幹部からは新しく小枝が伸び、民家の敷地内にあるものの外から見ることはできます。
天然記念物として町指定重要文化財(昭和58年12月指定・平成4年1月解除)となり、ひろしま県民文化百選(花と木百選 昭和62年)の選定を受けるなど、広く町民のくらしの中で親しまれてきた当時の姿をしのぶものです。
 倒壊前のムクノキ
倒壊前のムクノキ
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
出合清水・今出川清水の名称(位置)訂正
出合清水・今出川清水の名称(位置)訂正の説明会を平成24年11月17日に開催しました。
会場:くすのきプラザ 1階 『ギャラリー』
講師:府中町文化財保護審議会 会長、島根県立大学名誉教授 横田 禎昭
出席人数:23人

※説明会資料をPDF形式で閲覧することができます。
ダウンロード
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
千代城跡(せんだいじょうあと)
 千代山に築かれた白井賢胤の拠城跡です。出張城の支城的役割を果たしていたものと推測されています。
千代山に築かれた白井賢胤の拠城跡です。出張城の支城的役割を果たしていたものと推測されています。
芸藩通志〔文政12年(1829年)〕の府中村絵図に「千代山・古城跡」と記されています。
天文年間(1532~1554年)大内、毛利両軍の攻撃により出張城主白井氏が没落した後も一族の白井万五郎が一時居城し、のちに毛利氏に降ったといいます。
以前は鹿籠山と陸続きであったもののJR山陽本線の敷設によって分断されました。昭和初期には廓と見られる平坦地や、中腹には稲荷社が祀られていましたが、現在は住宅や工場が建ち並び城跡としての面影はありません。
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
国庁屋敷跡・田所明神社と田所文書(広島県重要文化財)
 平安時代末期から鎌倉時代にかけて安芸国の有力な在庁官人(国司の庁に勤務し、事務を行う役人)で、田地に関する行政機関(田所)の長官的職務にあった田所氏の館跡と伝えられ、同家に伝わる田所文書に国庁屋敷1丁と記されています。(平安時代中期頃から国司は任命されても赴任せず、留守所を置いて在庁官人と呼ばれる地方豪族にその国の政治を任せるようになっていました)
平安時代末期から鎌倉時代にかけて安芸国の有力な在庁官人(国司の庁に勤務し、事務を行う役人)で、田地に関する行政機関(田所)の長官的職務にあった田所氏の館跡と伝えられ、同家に伝わる田所文書に国庁屋敷1丁と記されています。(平安時代中期頃から国司は任命されても赴任せず、留守所を置いて在庁官人と呼ばれる地方豪族にその国の政治を任せるようになっていました)
屋敷跡には現在も田所氏の子孫が居住し、鎌倉時代の府中や安芸国の田・畠などの状況を物語る貴重な史料「田所文書」を伝え、この田所文書は昭和44年(1969年)広島県重要文化財に指定されています。
田所明神社
 田所文書(レプリカ) 第1巻「安芸国衙領注進状」
田所文書(レプリカ) 第1巻「安芸国衙領注進状」
安芸国諸郡の郷、村、名ごとに国衙領の面積とその内訳の各種免田と輸租田を列記した鎌倉時代の注文書。
 田所文書(レプリカ) 第2巻「田所沙弥譲状」
田所文書(レプリカ) 第2巻「田所沙弥譲状」
正応2年(1289年)の奥書があり、田所氏が勤めるべき諸職務の内容、府中、船越村、原郷、三田郷、温品村その他に散在する数十町歩の私有地、数十人におよぶ所従など田所氏の財産を書き上げたもの。
関連情報
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
ページの先頭です。メニューを飛ばして本文へ
鹿籠清水(こごもりしみず)
 鹿籠清水は丘陵状の鹿籠山南麓に湧き出る泉で、地元の人たちには清水川と呼ばれていました。
鹿籠清水は丘陵状の鹿籠山南麓に湧き出る泉で、地元の人たちには清水川と呼ばれていました。
天保年間(1830~1844年)の図面にも載っており、古くから生活用水として使用されていたことがわかります。
湧水池、洗い場があり、以前は水量が豊富で特別に掃除などしなくとも清潔が保たれ、ひどい干ばつの年など近辺の井戸は枯れてもこの泉の枯れることはなかったと伝えられていますが、今は宅地造成などで水量も減り使われることはなくなりました。


 Home
Home




コメント
コメントを投稿