सूर्य की त्रिज्या लगभग 700,000 किमी और व्यास लगभग 1,400,000 किमी है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है।



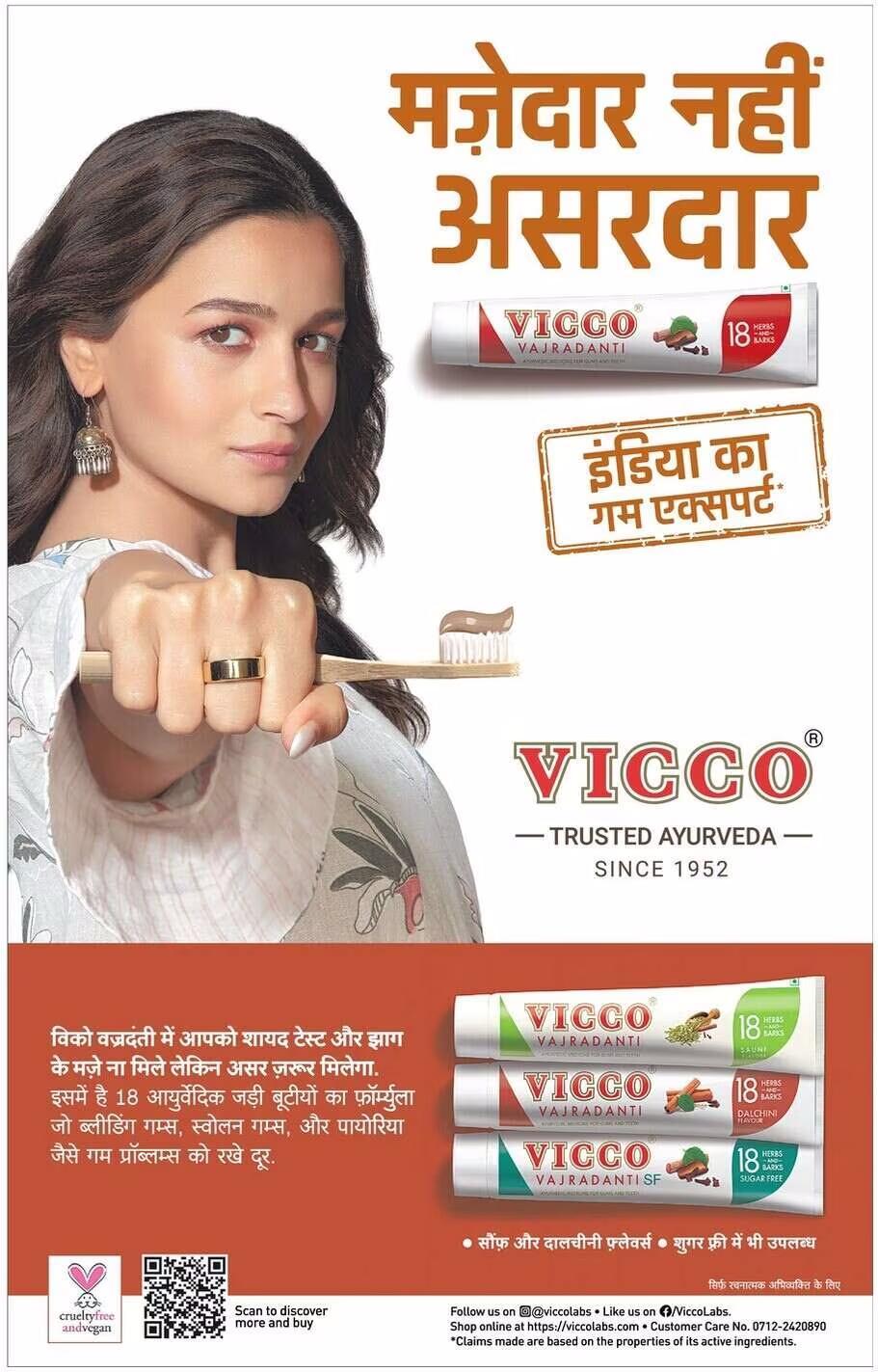


出合清水(であいしみず)
 この清水は水分峡を源とし、近くには総社跡や国庁屋敷(田所屋敷)跡などがあり、神聖な水として神饌に供えられ、また近隣住民の生活用水としても昔から使われていたといいます。
この清水は水分峡を源とし、近くには総社跡や国庁屋敷(田所屋敷)跡などがあり、神聖な水として神饌に供えられ、また近隣住民の生活用水としても昔から使われていたといいます。
たびたびの水害で埋没したこともあったものの、その都度地区の人たちの手で掘り返され、湧水としてよみがえったそうです。
「大己豊前諸書附写」に、安政6年(1859年)芸州藩主浅野茂長が長福寺、道隆寺に参詣し、出井、今出川にも立ち寄った、という記録が残っています。
現在は民家の一角にあります。
古歌
安芸の国府 出合清水に今出川 温品あらし いつもはげしき
出張城跡(ではりじょうあと)
 目の前に多家神社と長福寺の森が広がる標高34.5メートルの独立丘です。
目の前に多家神社と長福寺の森が広がる標高34.5メートルの独立丘です。
室町時代の中ごろ応永年間(1394~1428年)に安芸守護武田氏に従って下総国(現千葉県)から西下してきた白井加賀守胤時が初代城主となった城跡で、以後170年間に渡って府中を中心に領内を治めたと伝えられています。
中世の史料では府城、国府城、芸府城などと記されており、現宮の町一丁目と同三丁目の境の古山陽道沿いを出張市と呼んでいたことから、出張城は近世の字名からとったものと思われています。
 大正時代(1912年~1926年)には、馬場、門の跡が残っていたといわれますが、開墾等(古城具、墓石、人骨等が掘り起こされたという)により、今は城跡は本丸の跡を中心に数段地が残っているだけです。
大正時代(1912年~1926年)には、馬場、門の跡が残っていたといわれますが、開墾等(古城具、墓石、人骨等が掘り起こされたという)により、今は城跡は本丸の跡を中心に数段地が残っているだけです。
白井加賀守親胤の名が刻まれている石碑が残っています。
白井氏系図記事に、「寛永3年(1462年)白井親胤府中出張城に拠り、武田元信に属す」とあります。
[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
白井 親胤
しらい ちかたね
15世紀後半の仁保白井氏の当主。加賀守。光胤の父。武田氏の被官。近世の萩藩閥閲録に記載された白井氏家譜に挙げられた歴代当主の内、史料上で確認できる最も古い人物。
仁保白井氏の権益
明応四年(1495)十月、安芸分郡守護・武田元信は白井光胤に対し、父親胤の「安芸国仁保嶋海上諸公事」と「同(仁保嶋)飯山後浦悉大河迄」ならびに「府中散在分古市村等事」を相続することを安堵している(『安芸府中町史』資料編57 岩瀬文庫所蔵文書白井文書)。
「仁保嶋海上諸公事」とは仁保島周辺海域を航行する船舶からの「公事」(通行料)徴収権とみられる。「飯山」、「後浦」、「大河」は仁保島の地名。これらのことから、当時の仁保白井氏が仁保島を拠点にして既に周辺海域を支配していたことがうかがえる。
なお、光胤への安堵状が発給されているということは、親胤はこのとき既に隠居ないし死没していたと思われる。
彼らの動向をまとめ上げ、武家の棟梁となる機会は頼朝以外の人、例えば源義仲・源行家、あるいは平宗盛にも与えられていた。頼朝が内乱に終息をもたらし得たのは、彼こそが在地領主層の要望に最もよくこたえたからである。この意味で幕府の成立は、時代の画期ととらえることができる。なお、当時の合戦についてであるが、軍記には、例えば富士川の戦いは平家軍7万騎・源氏軍20万騎などと記されている。これは大変な誇張であり、保元の乱のときの平清盛軍300騎・源義朝軍200騎、という数字を参照すると、実数は10分の1以下であったろう。
平氏に反する勢力のうち、とくに強大だったのは源頼朝(1147〜1199)の勢力である。頼朝は源義朝の子で、平治の乱のあと伊豆に流されていた。以仁王の令旨を叔父源行家から伝えられ、1180(治承4)年8月、妻北条政子の父北条時政(1138〜1215)らと挙兵した。
石橋山の戦いでは平氏方の大庭景親らに敗れて海路阿波国に逃れたものの、代々源氏に使えていた東国の武士が続々と馳せ参じ、早くも10月、頼朝は源氏の根拠地であった鎌倉に入った。平清盛は孫の平維盛を大将として頼朝追討の大軍を東国に派遣したが、平氏軍は駿河国の富士川で源氏の軍に大敗して京都に逃げ帰った。水鳥の飛び立つ音に驚き、源氏の夜襲と間違えて敗走したといわれる。頼朝は配下の武士たちの要望を入れてあえてこれを追いかけることをせず、鎌倉に帰って東国の経営に専念した。東国平定に失敗した平氏は、建設中の摂津福原京を放棄してやむなく京都に帰り、以仁王に加担した大寺社を焼き討ちし、近江・河内の源氏の一族を討伐して畿内の支配を固め、諸国の動乱に対処しようとした。
だが、1181(養和元)年閏2月の清盛の死と同年の畿内・西国の大飢饉(養和の飢饉)が、平氏に深刻な打撃を与えた。
福原京遷都
以仁王が敗死した翌6月、平清盛は安徳天皇・高倉上皇を奉じて摂津の福原京に遷都した。平家の指導力を高めるための措置であったが、貴族たちの反発は激しく、南都・北嶺の僧兵や近江・河内の源氏の反平氏の動きも活発になった。そのため清盛はやむなく新都造営を中断し、11月には都を京都に戻すことにした。
源頼朝の従弟源義仲(1154〜1184)は、頼朝より1ヶ月ほどのちに信濃国で挙兵した。徐々に近隣の武士を従え、1181年6月、平氏の命を受けた越後の豪族城氏の攻撃を退けて北陸道に進出した。北陸道諸国には反平氏の気運が高まっており、義仲の勢力は急激に大きくなった。
1183(寿永2)年、平氏は再び平維盛を大将として軍勢を北陸に派遣したが、越中にいた義仲は加賀と越中の国境砺波山の倶利伽羅峠で迎え討ち、これを撃破した。牛の角にたいまつを結んで夜襲をかけたと伝えられる一戦である。
義仲は敗走する平氏軍を追って加賀国篠原でも勝利し、そのまま京都に攻め上がった。畿内の武士や寺社勢力も一斉に平氏に反旗を翻し、同年7月、平氏一門はついに京都から追い落とされた。
都での源義仲は政治的配慮に乏しく、後白河法皇の反感をかい、反平氏勢力の掌握に失敗した。彼が平氏を打つべく中国地方に滞在する間に、法皇は源頼朝の上京を促した。頼朝は弟の源範頼と源義経を大将として東国の軍勢を派遣した。源義仲は急ぎ防戦したが、味方となる武士は少なく、1184(寿永3、元暦元)年1月、近江国粟津で戦死した。
源氏が相争っているうちに、平氏は勢力を回復して福原に戻り、京都帰還の機会をうかがっていた。後白河法皇は平氏追討の院宣を源頼朝に与え、源氏軍はただちに平氏の拠点一の谷を攻撃した。1184年2月の源平両氏の命運を賭けた戦いは、源義経の活躍を得て源氏側が勝利した。頼朝はこののち各地に有力な武士を派遣し、平氏や源義仲の勢力を掃討させた。平氏の基盤である四国・九州の武士も頼朝に臣従するようになった情勢をみて、1185(文治元)年2月、源義経は讃岐国屋島に平氏を急襲し、さらに長門国壇ノ浦に追い詰めた。源義経との海戦に敗れた平氏一門は、同年3月、安徳天皇とともに海中に没した。
源頼朝の勢力増大を恐れた後白河法皇は、軍事に優れた源義経を重く用い、頼朝の対抗者にしようと試みた。頼朝は法皇の動向を警戒し、凱旋する義経を鎌倉に入れず、京都に追い返した。法皇は義経と叔父源行家に九州・四国の武士の指揮権を与え、頼朝追討の命令を下した。しかし武士たちは頼朝を重んじて法皇の命令を聞かず、義経は孤立し、奥州平泉の豪族藤原秀衡のもとに落ち延びた。秀衡の死後、その子の藤原泰衡は源義経を殺害して頼朝との協調をはかったが、頼朝は自ら大軍を率いて奥州に進み、藤原氏一族を滅ぼした。1189(文治5)年のことである。これにより、武家の棟梁としての頼朝の地位を脅かすものは誰もいなくなったのである。

 トップページ
トップページ 


コメント
コメントを投稿